「夜になると何度も泣いて起きる」「授乳しても抱っこしても泣き止まない」「自分も寝不足で気持ちがついていかない」
――赤ちゃんの夜泣きは、多くのママ・パパが経験する大きな悩みです。
本記事では、赤ちゃんの夜泣きの原因と、家庭でできる具体的な対策を詳しく解説します。
さらに看護師としての知識と母としての実体験を交えて、ベビーマッサージを取り入れる方法も紹介します。
はじめに

また…?もう起きたの?
24時間毎日大切な我が子と過ごして幸せなはずなのに、寝不足でイライラする日々。
なんで寝てくれないの?
おむつは替えたし、ミルクもあげた。
もう何時間も抱っこしてる。
赤ちゃんも寝てる時間が少ないけど大丈夫なの?
私自身、娘が赤ちゃんだった頃、夜中に1時間おきに泣かれて寝不足の日々を過ごしていました。
翌日も家事や育児に追われてイライラし、夫とぶつかることもありました。
子どものために頑張りたいのに、心と体がつらくなる…そんな経験は珍しくありません。
● 現在子育て中の方
● 夜泣きで寝不足な日が続いている方
● 赤ちゃんの睡眠時間も、私の睡眠時間も確保したい
● 赤ちゃんがよく寝るベビーマッサージを知りたい
私の体験談
私の娘は生後7か月頃から夜泣きが始まりました。
毎晩1時間おきに泣かれて、当時は本当に心が折れそうでした。
その頃ベビーマッサージの資格取得しようと勉強した真っ最中でした。
習ったベビーマッサージを夜寝る前に取り入れてみたところ、徐々に眠りが深くなり夜中に起きる回数が減っていきました。
「マッサージをしても泣くときはある」けれど、「安心して眠れる回数が増えた」ことは、親にとって大きな救いでした。
赤ちゃんの夜泣きとは?
夜泣きの定義
-
生後4〜6か月頃から1歳半ごろによく見られる
-
昼間は元気なのに、夜だけ急に泣き出す
-
授乳や抱っこでもなかなか落ち着かない
つまり、病気ではなく 成長過程で一時的に起こる現象 であることが多いです!
長時間我が子に泣かれると病気なんじゃないかと心配になりますよね。
しかし夜泣きも成長の証!我が子にとって正常な現象のようです。
なぜ夜泣きが起こるの?
-
赤ちゃんの睡眠リズムはまだ未熟
-
昼間に受けた刺激(人や音、光)が夜に処理しきれず興奮
-
歯の生え始めや成長痛など身体の不快感
-
「ママがいないと不安」という心理的要因
夜泣きは「赤ちゃんの発達の一部」でもあるため、必ずしも異常ではありません。
大人ではあまり気にならないことも、安全なママのお腹の中から出てきた赤ちゃんからすれば不快に感じたり・不安を感じてしまうようです。
ここから夜泣きの原因とその特徴の理解を深めていきましょう!

夜泣きの主な原因と特徴
このように夜泣きの原因は ひとつではなく複数が絡み合っている ことがほとんどです。
「眠りが浅いタイミングで環境が不快 → 不安が強まる → 泣く」といった連鎖が起こるため、原因を一つひとつ減らしていくことが改善への近道になります。
1. 睡眠リズムの未成熟
赤ちゃんの睡眠は大人と大きく異なります。
大人は約90分ごとに浅い眠り(レム睡眠)と深い眠り(ノンレム睡眠)を繰り返していますが、赤ちゃんのサイクルは わずか40〜50分。
そのたびに眠りが浅くなり、目を覚ましてしまうのです。
特に生後6か月ごろまでは昼夜の区別がつきにくく、夜中に目覚めるのは自然なこと。
浅い眠りに入ったときに「暗い・静か・ママがいない」と不安を感じて泣く、これが夜泣きの大きな原因のひとつです。
2. 成長や発達の影響
赤ちゃんは日々、新しいことを覚えていきます。
寝返りやお座り、はいはい、つかまり立ちなどの大きな発達があると、脳が興奮して眠りが浅くなることがあります。
「できるようになったことを、寝ながらも無意識に繰り返してしまう」ことがあり、それが夜泣きにつながるケースも。
実際に「寝返りができるようになったら夜泣きが増えた」という声は多いです。

寝ながら繰り返すって可愛い♪
3. 環境の変化
赤ちゃんは大人以上に環境の変化に敏感です。
-
室温が暑すぎる、寒すぎる
-
エアコンや扇風機の風が直接あたっている
-
部屋が明るい/物音がする
-
昼間に人混みや外出で刺激を受けすぎた
こうした要因は、眠りの質を妨げて夜泣きの引き金になります。
大人にとっては些細に思えることでも、赤ちゃんには大きなストレスなのです。
4. 心理的要因
生後6〜9か月ごろから「分離不安」という心理が芽生えます。
これは「ママやパパがそばにいないと不安で泣いてしまう」という成長過程で自然に出てくる反応です。
昼間はニコニコしているのに、夜中にふと目が覚めた瞬間にママがいないと強く泣くことがあります。
これは「母親との絆がしっかりできている証拠」でもありますが、親にとっては大変な時期でもあります。
5. 身体的な不快感
夜泣きのように見えて、実は体の不快感が原因のこともあります。
-
おむつが濡れている
-
便秘でお腹が張っている
-
歯が生えてきてムズムズしている
-
風邪の初期症状や耳の痛み
この場合泣き方が普段より強く長引くことが多いので、注意深く観察することが大切です。
また足や手の指に髪の毛が絡まり指先がうっ血していることもあるため、指先まで観察することをおすすめします。
今日からできる夜泣き対策
1. 環境を整える
「寝室=落ち着ける場所」と赤ちゃんが認識できるようにすることが大切です。
2. 入眠ルーティンをつくる
毎晩同じ流れで寝かせると、「そろそろ寝る時間」と体が覚えます。
習慣が安心感を与え、夜泣きの頻度を減らす効果が期待できます。
3. 抱っこ・授乳以外の方法も試す
授乳や抱っこだけに頼らない工夫をすると、ママの負担も減ります。
赤ちゃんによって安心材料は様々です。
換気扇の音や洗濯機の音、食洗器の音で安心して眠る赤ちゃんもいます。

娘は洗濯機の音でよく寝ました。
4. 親も無理をしない
親の休息が、長い夜泣き期を乗り越えるカギになります。
夜泣きもいつかはなくなります。
しかしいつ終わるかわからないのが、辛くなる原因の大きな1つだと思います。
しっかり睡眠時間を確保してあげたい。
イライラせず余裕をもって我が子に関わりたい。
そのためには赤ちゃんよりもまずママやパパが無理をせず休息の時間を作るということです。

私は好きな映画を観ながら寝かしつけていました。
100%赤ちゃんに向き合わないといけないわけではありません。
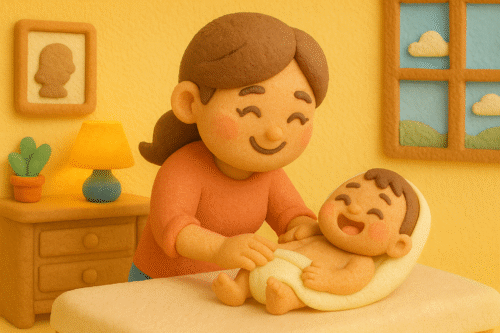
ベビーマッサージでできる夜泣きケア
マッサージが夜泣きに効果的な理由
-
やさしい刺激が赤ちゃんの体をリラックスさせる
-
自律神経を整え、眠りのリズムを安定させる
-
親子のスキンシップで安心感が高まり、夜中に目覚めても落ち着きやすい
「寝る子はよく育つ」といいますが、これはメラトニンという成長ホルモンが、睡眠中に分泌されることからそのように言われるようになりました。
ベビーマッサージは、このメラトニンを高めることが研究結果で報告されています。
メラトニンは「眠る」「起きる」という睡眠と覚醒のリズムを整える働きをしますが、赤ちゃんの就寝時にマッサージを行うことで、このメラトニンが増加し、より深く寝入り目も覚めやすくなるというわけです。
簡単にできるマッサージ例
-
足のマッサージ
太ももから足首に向かって優しくなで下ろす -
お腹のマッサージ
「の」の字を描くように時計回りにくるくるとなでる -
背中のマッサージ
首のつけ根から腰まで手のひらでなで下ろす
オイルは使用しても、しなくてもいいですが、オイルを使用する場合はお風呂上りだと保湿の延長で行えます。
使用するオイルは「ホホバオイル」や「グレープシードオイル」など、無添加・無着色・無香料で植物性のオイルを選択し、使用する前にパッチテストを行いましょう!
受診が必要なケース
夜泣きだと思っていても、以下のような症状がある場合は小児科受診をおすすめします。
-
発熱、咳、下痢、嘔吐を伴う
-
泣き方が普段と違い、激しい・長時間続く
-
血便や血尿が見られる
-
日中も不機嫌で元気がない
何かいつもと違うなという直感が働いたら、躊躇せず病院に行きましょう。
まとめ
赤ちゃんの夜泣きは多くの家庭で経験するものですが、原因を理解し、工夫を取り入れることで改善につながります。
-
環境を整える
-
入眠ルーティンをつくる
-
抱っこや授乳以外の工夫を試す
-
親も休む工夫をする
-
ベビーマッサージを取り入れる
夜泣きは一時的なものであり、必ず落ち着く時期がきます。
親が疲れ切ってしまう前に、できる工夫を試してみましょう。
👉 私のベビーマッサージ教室では「夜泣き改善に役立つマッサージ方法」も実際に学べます。
オンラインでも実施してますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。



コメント